様々な心理療法で、「まず自分が受けること」の意義が言われます。
私も、臨床動作法やソマティック・エクスペリエンシング等を学び、実践する者として、
少しずつ自分自身もセラピーを受けつつ、あります。
(※ソマティック・エクスペリエンシングについてはSEP資格取得研修受講中なので、今現在私は無資格です)
しかし、先達からのSVやコンサルテーションを受ける積極性に比べ、自分がセラピーを受けるのがあまり進みません。
それについて先輩心理士とのやりとりや、改めて自身を振り返ったことを書き連ねたいと思います。
もし、同様のひっかかりのある方への参考になれば。
そして私自身が今何を考え、何を感じているか整理するために。
自分が志すセラピーを受ける意義
先輩心理士と話す中、出していただいた例えがこちらでした。
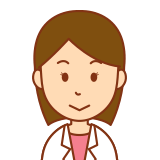
日本に来たことがない外国人が、
食べたこともなく、味も知らない日本料理を、
美味しいと言って客に出す。
ようなものかもね
先輩との雑談の中から
カウンセリングを通して、非常に生々しい体験をクライアントさんはされます。
その生々しさを実感して言うセラピストの一言と、上辺だけの一言は、伝わるものが違うかもしれません。
違う、というよりも、言語という音声を伝って、セラピストの心にあるものが、隠さず伝わる、といった方が適切かもしれません。
動作法やソマティック・エクスペリエンシング等、言語だけでなく、身体・神経へのアプローチを重視するようなものは特にそうかもしれません。
特に、いわゆる状態が重いクライアントさんほど、言葉の内容よりも、セラピストの内にあるものが敏感に伝わるようです。
自分がセラピーを受ける際のコツ?
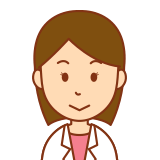
私が言える、役に立つかもしれない唯一のコツは、
「あなた個人が、クライアントとしてセラピーを受ける」
ことだと思うよ。
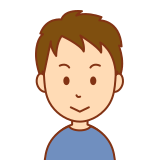
どういうことですか
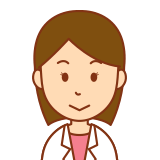
例えば、あなたのクライアントさんが、
勉強のためだ、とか
構えてカウンセリングを受けていたら、どうする?
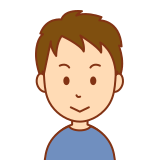
うーん…
状況次第ですが、
そういった構えを解けるようにアプローチするところから始まります。
無事、構えが解けてから、カウンセリングが開始される、かなあ。
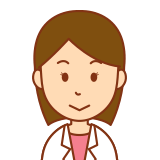
それと同じじゃないかな。
「これは勉強のためだ」とか、
そういう見方は、あなた自身が生々しく体験ができない。
逆にセラピーが下手になっちゃうかも。
頭であーだこーだ考えるんじゃなくて、
まずは一個人、あなたがどんな体験をするのか、
生々しく、感じてほしい。
浮かんだイメージ
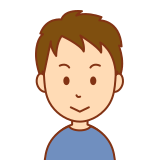
なんだか、
「動物を見る時に、
ガラス越し、安全圏、外から動物を眺める動物園に行くのか、
野生動物の生き様を現場で見に行くのか」
の違いのような
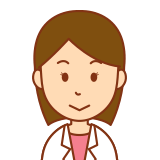
面白い例えだね。
これ以上は言葉を重ねても、あまり有意義にはならなそう。
今、ここであなたが感じたことを、大切にして。
たぶん、私からセラピーの指導やコンサルを付け焼き刃でするより、
何百倍もセラピーがうまくなるよ。
私の中の「セラピーを受ける」ひっかかり
冒頭のように、私は、SVやケースコンサルを受けることに比べ、自分がセラピーを受けることに、何かためらいがあります。
忙しいから、何をテーマにしていいのかわからない、そんな気持ち。
ですが、先輩とのやりとりで、何か、言葉にならない何かが生じています。
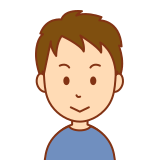
今、こうして、何かひっかかりがある。
色々言い訳をつけて避けてる自分がいる。
そのことを、一緒に、好奇心を持って、観察してもらえるセラピーを受けたいな。
そういえば、今、コンサルテーションを受けている別の先輩に同じことを相談したら、上記私の気づきを、大切に扱う時間にしたらいいんじゃないか、といったコメントをいただいたことを思い出しました。
おまけ?伊藤絵美先生のバンジージャンプ
これ以上は話さない、と言いつつ、後輩思いな先輩は、その後もしばらく話してくれました。
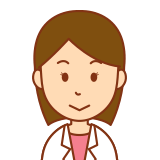
ま。色んなセラピーは、大なり小なり、クライアントさんに生々しく体験を起こして、何かを乗り越えたり、時にはものすごい負担をかける。
そこをセラピストが実感して励ますのと、上辺だけ一緒に頑張りましょうとか言うのでは、全然違うよ。
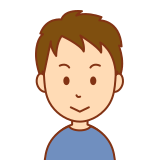
私が志すセラピーにより起こる体験を、
私自身が耐えられないなら、
そのセラピーは行うべきではない、と感じました。
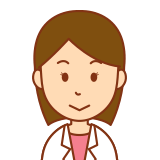
そういうことだね。
「自分がやられて嫌なことは、人にしてはいけない」
幼稚園生も知っている対人関係の基本だよ。
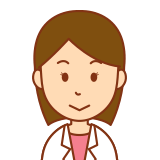
そう思うと、認知行動療法をやられている、
伊藤絵美先生。
あの方、私は会ったことないけど、
あるエッセイを読んで、心から尊敬してる。
なんてタイトルだったかな。
「マカオ バンジー 伊藤絵美」とかで探すと出てくるかも。
興味があったら調べてみて。
調べてみたら、ありました。
ご興味がありましたら、ググってみてください。
私も会ったこともなく、勝手に読んで、勝手に感銘を受けました。
私にとってのバンジージャンプは、なんだろう。
ここまでご覧いただき、ありがとうございます。
このブログが、あなたがあなたらしく生きるための土台作りの、何かのヒントになれば幸いです。
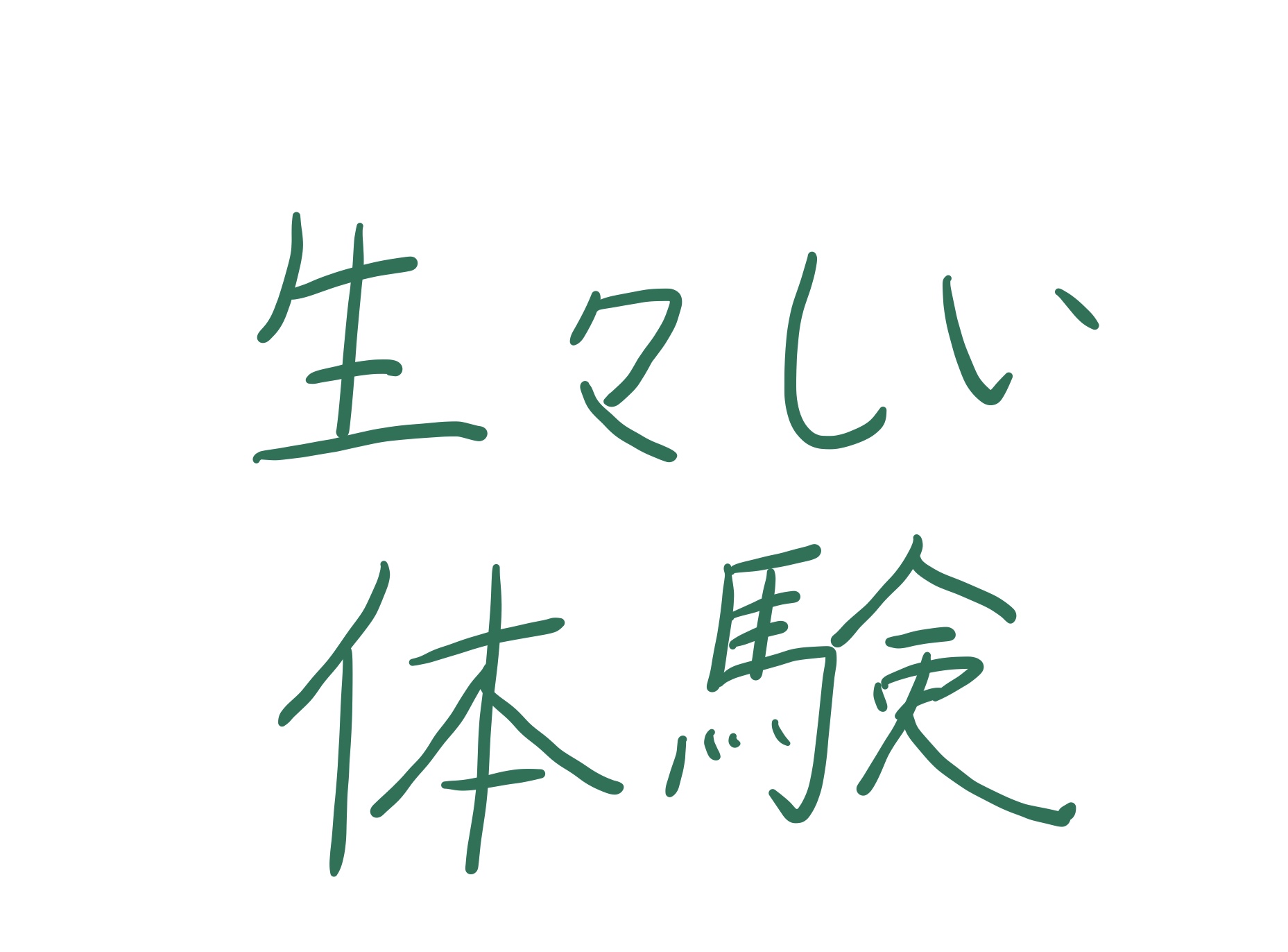


コメント